アパート経営を続けていると、個人事業主のままで良いのか、それとも法人化すべきか悩む方も少なくありません。
所得が増えるにつれて税負担は重くなり、また将来の相続を考えると早めの対策が重要です。
法人化の適切な時期やメリット・デメリットを理解することで、最適な経営戦略が見えてくるでしょう。
アパート経営の法人化に関して、多くの方が抱える悩みや疑問を解説します。
Contents
アパート経営における法人化とは?
そもそも法人化とは、会社を設立し、会社名義で経営を行うことです。アパート経営による利益は法人の収益とみなされるため、法人税などが課税されます。
まずは法人化する際の判断基準、個人から法人化する手順について解説します。
法人化する目安
結論として、アパート経営の法人化がおすすめできるのは「個人よりも法人としてアパート経営をするとメリットが大きい場合」です。判断基準として2つの例を紹介します。
1つ目はアパート経営による所得が一定額を超える場合です。
個人の所得税は所得が一定額を超えると、超えた部分により高い税率が適用される「超過累進課税制度」が採用されています。一方で、法人税の税率は原則的な税率と軽減税率の2種類のみです。
所得が少ないうちは所得税のほうが税率は低いですが、所得が高くなると法人税の方が低い税率となります。具体的には、所得が900万円を超えると、所得税率は33%、法人税率は23.2%で法人税の方が低くなります。
そのため、個人の方で所得が900万円を超える場合は、法人化した方が税金面で有利です。あくまで目安ですが、所得が600〜800万円を超えたあたりから、法人化を検討し始めてもよいでしょう。
2つ目は相続財産が多い場合です。
アパート経営を個人として行なっている場合、アパートも相続財産として相続税の課税対象です。相続財産の総額や相続人の人数にもよりますが、相続税の負担が重くなってしまう恐れがあります。
法人化すればアパートは法人の所有物となるため、経営者個人が亡くなっても相続財産として扱われません。そのため、個人で賃貸経営をする場合よりも相続財産が少なくなり、相続税の節税にもつながります。
個人経営から法人化する方法
アパート経営で個人経営から法人化に変更する際の流れをご紹介します。
- 会社の商号、本店所在地、資本金の額など会社の基本情報を決める
- 会社用の印鑑を作成する
- 定款の作成および定款認証を行う
- 資本金の払込をする
- 法務局で会社設立の登記申請をする
会社設立手続きの完了後、アパートの経営者を個人から法人に変えるための作業を進めます。
不動産所有者の名義を勝手に個人から法人へ変えることはできません。個人から法人へ不動産を贈与する、もしくは個人と法人の間で不動産の売買取引を行う必要があります。
また、不動産オーナーの変更に伴い、各種契約の名義変更など諸手続きも必要です。
アパート経営で法人化した場合の相続税対策
アパート経営を法人化することで相続税の節税対策ができる可能性が高くなります。
相続税対策につながる理由を3つご紹介します。
アパートを相続財産ではなく株式にできる
個人でアパート経営をしている場合、対象のアパートがそのまま相続財産となります。
アパートの相続は、以下のような理由から相続人に負担がかかってしまう可能性が高いです。
- 相続税評価額の計算や書類の取り寄せなど手間がかかる
- 不動産は現金や株式のように均等に分けにくいため、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議でのトラブルを招く恐れがある
- 相続登記の手間やコストが発生する
アパート経営を法人化すれば、不動産ではなく株式として相続できます。遺産分割や名義変更などの懸念が解消されるため、相続関連で相続人同士が相談するなどの負担を軽減できるでしょう。
家賃収入を役員報酬として家族に分配できる
アパート経営を法人として行えば、会社からの役員報酬という形で家賃収入を家族に分配できます。
結果として得られる具体的なメリットは以下の3つです。
- アパート経営による家賃収入が個人名義の現預金にはならないため、相続財産となる現預金を減らせる
- 生前贈与に該当しない形で財産を移転できる
- 受け取った役員報酬を相続税の納税資金に充てられる
なお、上記のメリットを得るためには、家族が設立した会社の役員になる必要があります。
相続税評価額の減額が可能になる
被相続人が会社を経営していた場合、会社の株式が相続財産として扱われます。
株価算定には複雑な計算が必要ですが、簡単にいうと資産と負債の差額が株価相当額となるイメージです。
株価算定において用いるアパートの評価額は、アパートの所有期間によって以下のように異なります。
- 3年以下の場合:時価
- 3年を経過した後:相続税評価額
このようにアパート経営を法人化して3年が経過すると、個人と同じく相続税評価額で計算できます。そのため、相続対象となる株価の減額が可能です。
アパート経営で法人化した場合の節税方法
アパート経営の法人化は所得に対して課せられる税金の節税にも効果的です。
どのような効果があるのか詳しく解説します。
経営で赤字が発生しても繰り越せる
赤字の繰越期間は個人で最長3年、法人の場合は最長10年です。個人は赤字の繰越期間が短く、赤字の額によっては3年間で相殺しきれないケースもあります。
法人は繰越期間が最長10年と長く設定されているため、高額の赤字でも相殺しきれず無駄になってしまう可能性は低いでしょう。
所得税が減税しやすくなる
法人化によってアパート経営の所得税を減税しやすくなります。
主な理由として以下の3つが挙げられます。
- 所得が一定額を超えると所得税より法人税のほうが税率は低くなる
- 会社からの役員報酬に対して給与所得控除が適用される
- 役員報酬の額を自由に決められる
法人化すると、アパート経営による収入が個人の収入に直結する場合と違い、一度会社を経由することで所得のコントロールがしやすくなります。
また、会社からの役員報酬は給与所得に該当するため、給与所得控除の適用を受けられる点も大きなメリットです。
個人経営よりも経費で落とせる範囲が広くなる
同じアパート経営でも、個人経営より法人経営の方が経費で落とせる範囲が広くなります。
法人でのみ経費計上が可能な支出の例は以下のとおりです。
- 社会保険料(法人負担分)
- 役員報酬
- 社用車に関連する各種費用
- 出張旅費
- 法人名義の生命保険料
経費として計上できる支出が増えるため、個人経営の場合よりも課税対象となる所得を減らせる可能性があります。
アパート経営で法人化するときの注意点
アパート経営の法人化には、相続税や所得税の節税という面で多くのメリットがあると紹介しました。しかし、アパート経営の法人化には注意すべきデメリットも存在します。
この章では、法人化するときに気をつけるポイントを3つご紹介します。
条件を満たしていないと法人化できない
アパート経営の法人化が認められるのは、以下の条件をすべて満たした場合のみです。
- 法律に則った正しい手法で会社の登記手続きを完了させている
- アパートの所有者や賃借人名義などをすべて法人に変更している
- 法人として行うべき事務手続きや税務申告などを行なっている
形だけ会社設立をするのではなく、会社としてアパート経営を行うという実態が必要となります。
必ずしも節税できるとは限らない
アパート経営の法人化が必ずしも節税につながるとは限りません。
先に述べたように、所得が一定額を超えると所得税より法人税の方が低い税率になると紹介しました。言い換えると、所得が一定以下の場合は所得税の方が安く済むということです。
そのため、不動産所得が少ない状態で法人化すると、アパート経営の所得にかかる税金がかえって高くなることがあります。
また、法人化は必ずしも相続税の節税対策になるとは限りません。そもそも相続税は基礎控除をはじめ控除制度が多く設けられているため、控除によって税額がゼロになるケースもみられるからです。
アパート経営を個人で行なっていた場合でも、そもそも相続税が発生しない可能性も考えられます。アパート経営の法人化が本当に節税につながるか、事前にシミュレーションすることをおすすめします。
法人化するには費用と時間がかかる
株式会社の設立時に必ずかかる費用として以下の4つが挙げられます。
- 定款用収入印紙代
- 定款の謄本手数料
- 定款認証手数料
- 登録免許税
上記の費用だけでも合計20万円弱です。会社印の作成費用や税理士に設立の手続きを依頼した場合を考慮すると、合計25万円〜35万円程度になります。
また、会社設立では定款作成や法務局への登記申請などさまざまな手続きが必要です。
会社設立の検討を始めてから手続きがすべて完了するまで最短でも数日、長いと1カ月ほどかかる可能性もあります。
法人化を検討する際は、費用や手続きにかかる時間も考慮し、計画的に進めることが大切です。
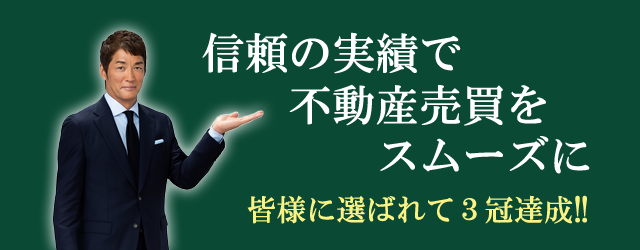

- 高値売却かつ早期売却したい方におすすめの不動産会社 No.1 ※
- 知人に紹介したい不動産売却会社 No.1 ※
- 相続の相談をお願いしたい不動産売却会社 No.1 ※
トップファーストでは、全国の一棟アパートや一棟マンションといった収益物件をはじめ、様々な不動産を取り扱っております。
相続や資産整理といった不動産に関するご相談も、実績豊富な当社にお気軽にお問い合わせください。高い専門知識を持ったスタッフが問題解決をお手伝いいたします。
2023年2023年5月期_ブランドのイメージ調査(調査1~3)
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査期間:2023年3月14日~2023年5月31日
n数:129(※調査1)、124(※調査2)、136(※調査3)/調査方法:Webアンケート
調査対象者:https://jmro.co.jp/r01446/
備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。


