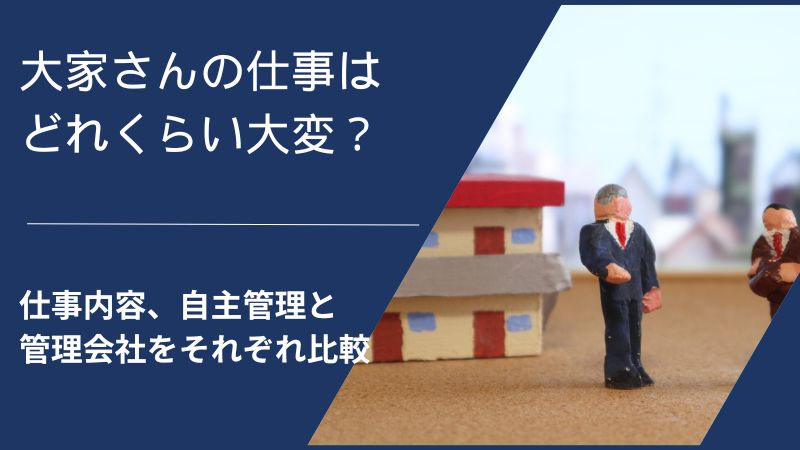大家として物件を管理する場合、物件の規模にもよりますが多くの手間と労力がかかります。
特に自主管理の場合は、入居者対応や修繕の手配など、幅広い業務を自分でこなす必要があります。
大家の仕事に興味がある方に向けて、主な仕事内容や自主管理と管理会社の比較を解説します。
大家の主な仕事や仕事内容
アパートやマンションなど不動産を持つ大家さんは、日々どのような業務を行っているのでしょうか。
自主管理している大家さんがどのような仕事をしているのか詳しく紹介します。
入居者の管理
賃貸物件の入居者は、基本的に不動産会社に依頼して募集を行います。
ちなみに、募集する前に家賃や敷金、礼金、入居の条件などを決めておく必要があります。
入居申込があったら、入居希望者がどんな人なのかを確認し、問題がなければ契約して入居してもらいます。
自主管理の場合は、入居者からクレームや相談、修繕依頼があった場合も大家さんが対応しなくてはいけません。
不動産の管理
自主管理の大家さんは物件の管理も自分で行いますが、主な業務は以下のとおりです。
- 廊下やエントランスなどの共用部分の清掃
- 電灯の交換など建物の保守・管理
- エレベーターの定期点検
- 電気やガス、水道などのトラブル対応
- 入居者が退去後の原状回復工事やリフォームの手配
原状回復は国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿い、経年劣化や通常損耗は貸主負担となるため、慎重に対応する必要があります。
そのため、不動産管理は慣れていないと時間がかかってしまうかもしれません。
資金管理
大家さんは毎月家賃が振り込まれているか確認したり、建物の修繕費や共用部の電気代といった必要経費などの帳簿を作成したりします。
家賃収入や経費の帳簿作成は、確定申告をする上でも必要な作業です。
また、固定資産税の支払いや大規模修繕に向けた積立資金への対応も必須です。
空室管理
入居だけでなく退去時の立ち会い、室内のクリーニングや修繕の手配も大家さんが行います。
空室の期間は家賃収入が得られないため、次の入居者を早々に募集する必要があります。
次の入居者を迎え入れるためにも、退去後の清掃作業や入居開始の準備をできるだけ早く進めることが大切です。
入居者の募集活動は不動産会社へ依頼したり、ポスターや看板を設置したり、募集サイトへ掲載したりとさまざまな方法があります。
自主管理と管理委託のメリットとデメリットを比較
自主管理とは大家さん自身が物件に関する全ての業務を行うことです。
一方、不動産会社や専門の管理会社に委託し、入居者や家賃の管理に対応してもらうことを管理委託と言います。
ここではそれぞれのメリット、デメリットについて詳しく比較していきます。
大家が自主管理するメリット
大家さんが自主管理することで得られるメリットについて詳しく解説します。
管理費用を抑えられる
管理委託では、大家さんの業務を代行してもらうため、管理委託手数料を支払う必要があります。
管理委託手数料は賃料の5〜10%が一般的です。しかし、自主管理であればそのような費用は一切かかりません。
たとえば、1つのアパートに6部屋あり、1部屋の家賃が5万円だとすると、毎月30万円の家賃収入です。
自主管理の場合は30万円が大家さんの収入になりますが、管理委託の場合は30万円のうち10%にあたる3万円を毎月支払う必要があります。つまり、年間で36万円の費用が発生するということです。
入居者とコミュニケーションがとりやすい
大家さんが対応窓口となるため、入居者との距離が近づきやすくなり、コミュニケーションがとりやすくなるのも利点です。
入居者との関係性が良くなれば、トラブルやクレーム、物件の不具合など何かあった時にいち早く情報を入手できるでしょう。
また、入居者も大家さんの顔が分かっていることで、物件を綺麗に使おうとしてくれたり、長く住んでくれたりといったメリットもあります。
大家が自主管理した場合のデメリット
自主管理のメリットがある一方で、もちろんデメリットもあります。
自主管理をした場合のデメリットについて詳しく見ていきましょう。
クレーム対応をする必要がある
管理委託の場合はトラブルの窓口は管理会社になりますが、自主管理の対応窓口は大家さんです。
そのため、入居者からのクレームやトラブル相談など、大家さんが1人で対応しなければなりません。
専門知識がなかったり、クレームを放置したりすると入居者の不満が高まり、関係悪化の原因になります。
不動産や生活に関する法律の知識を深め、クレームに対して迅速な対応が求められます。
資産価値が下がる恐れがある
賃貸物件を管理するための業務は多岐にわたります。
そのため、建物の清掃や点検が手薄になったり、他の業務が疎かになったりする可能性があります。
定期的な点検や清掃を怠ってしまうと、建物が劣化しやすくなり建物の資産価値が下がる恐れがあります。
管理委託に任せるメリット
管理委託する一番のメリットは、大家さんが時間や手間がかからないという点です。
メリットについて詳しく解説していきます。
自分で雑務を行う必要がない
管理業務を委託するということは、大家さんが入退去の立ち会いや手続き、建物の清掃や点検など雑務を行う必要がないということです。
クレームやトラブルの対応窓口も不動産会社ですので、会社員をしながら不動産経営したい人や、普段忙しくて急に対応するのが難しい方におすすめです。
入居者の募集対応もしてもらえる
管理委託では、大家さんが入居者の募集活動をする手間が省けます。
委託した不動産会社が、ポータルサイトやホームページに掲載したり、入居者募集の宣伝をしてくれたりとさまざまな方法で募集活動を行います。
管理委託に任せた場合のデメリット
管理委託の一番のデメリットは、毎月委託した会社に手数料を支払う必要があることです。
ほかにも、デメリットがあるので解説していきます。
手数料を支払う必要がある
前述のとおり、管理委託では管理委託手数料が毎月発生します。手数料の相場は、賃料の5〜10%程度です。
委託会社が回収した賃料から、手数料が引かれた金額が大家さんの収入となります。
そのため、手数料の支払いを考慮した家賃設定や資産運用を行う必要があります。
物件の状況が分かりにくい
県外や遠方の不動産を所有する大家さんにとって、管理委託は非常に便利な管理方法です。
しかし、大家さんが定期的に物件を確認できない場合、不動産会社が不都合な対応をしても気づきにくいというデメリットがあります。
会社が管理する物件は1つだけではありません。ほかに管理する物件が数多くあり、営業活動もある中で毎日物件を見回るのは難しいでしょう。
そのため実際に物件を見に行くと、雑草が生い茂っていたり、共用部の電灯が切れていたりと清掃や対応が不十分というケースもあります。
信頼できる管理委託会社を見極めるポイント
どの程度物件を丁寧に管理してくれるかは、管理会社や担当者次第です。
最後に信頼できる管理会社を選ぶポイントを紹介します。
手数料が適正な設定か確認する
管理会社に支払う手数料が適正な設定か必ず確認するようにしてください。
ここで注意しておきたいポイントとして、物件に空室があっても手数料は発生するという点です。
手数料の設定が高い会社の場合、空室が増えると赤字になる恐れがあります。管理委託の会社を選ぶときは、手数料が相場内に収まっている管理会社がおすすめです。
業務の対応範囲を確認する
管理委託といっても、管理会社によって対応してくれる業務範囲は異なります。
家賃の回収業務のみだったり、家賃の回収から建物の清掃や点検、クレーム対応まで全てを行ってくれたりと対応範囲はさまざまです。
契約前に、業務の対応範囲を必ず確認しましょう。管理業務の内容によっても手数料は変動するため、複数の会社と比較して適正か確認すると良いでしょう。
管理物件の入居率を確認する
不動産経営で大切なことは、空室期間をできるだけ短くすることです。まずは、管理会社が公開している入居率や平均空室期間を確認します。
管理会社の入居率とは、管理している物件数のうち入居状態にある部屋の割合のことです。
入居率が高いということは、それだけ空室の数が少ないということです。また、平均空室期間が短ければ、退去後に次の入居者がスムーズに決まっているということになります。
管理会社の対応が悪いと、入居率が低かったり平均空室期間が長くなったりする可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
管理の負担が大きい場合は売却も選択肢
管理委託の業務内容や手数料は会社によって大きく異なります。手数料が安いからといって、大家さんが対応する業務が多くなってしまうと本末転倒です。
賃貸物件を管理するのが厳しいと感じたときは、物件を売却することも一つの方法です。
売却することで大家としての負担から解放されるだけでなく、新たな投資や資産活用など選択肢を広げられます。
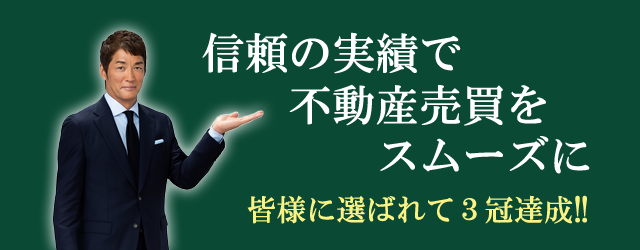

- 高値売却かつ早期売却したい方におすすめの不動産会社 No.1 ※
- 知人に紹介したい不動産売却会社 No.1 ※
- 相続の相談をお願いしたい不動産売却会社 No.1 ※
トップファーストでは、全国の一棟アパートや一棟マンションといった収益物件をはじめ、様々な不動産を取り扱っております。
相続や資産整理といった不動産に関するご相談も、実績豊富な当社にお気軽にお問い合わせください。高い専門知識を持ったスタッフが問題解決をお手伝いいたします。
2023年2023年5月期_ブランドのイメージ調査(調査1~3)
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査期間:2023年3月14日~2023年5月31日
n数:129(※調査1)、124(※調査2)、136(※調査3)/調査方法:Webアンケート
調査対象者:https://jmro.co.jp/r01446/
備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。