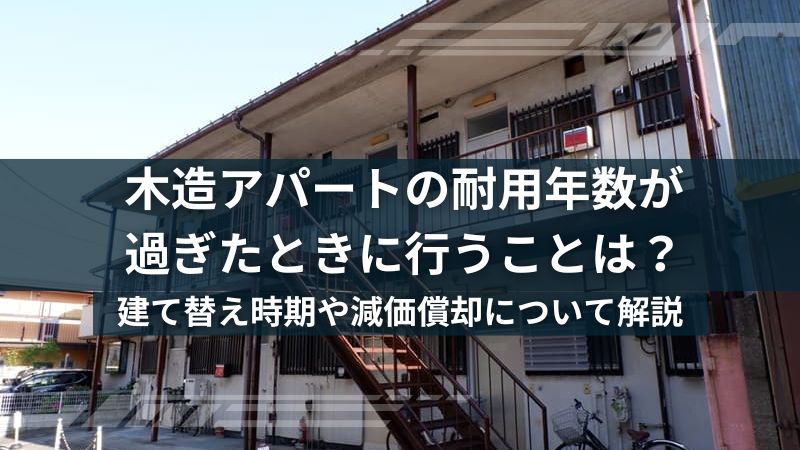木造アパートの経営をする中で、「耐用年数」という言葉が気になった方もいるでしょう。税務上、木造アパートの耐用年数は22年と定められており、この期間を過ぎると帳簿上の価値は0円となります。
しかし、これはあくまで税務上の話であり、実際は22年を過ぎてもアパート経営を続けることは可能です。
ただし、耐用年数が過ぎると修繕費や空室リスクなどの課題が増えるため、具体的な対応策を知っておくことが重要です。木造アパートにおける耐用年数の概要、耐用年数を過ぎたときの対処法について詳しく解説します。
木造アパートの耐用年数とは
木造アパートは、国税庁が定める「減価償却資産」に分類されるため、耐用年数が設定されています。減価償却資産とは、時間の経過とともに価値が減少資産をしていく資産を指し、建物や車両、設備などが含まれます。
木造アパートをはじめとする不動産の場合、物件の購入や維持費などかかった経費を一度にすべて計上するのではなく、耐用年数を基に分割して計上しています。
例えば、耐用年数が10年の不動産を2000万で購入した場合で考えてみましょう。
10年の中で1年だけ2,000万の出費があると帳簿に計上した場合、収支が大きく変動したことになります。一方、10年間、毎年200万円を減価償却費として計上することで収支を均一化でき、経営状況を理解しやすくなるでしょう。
そのため、木造アパートの耐用年数は、収支計画や税務管理するための重要なポイントです。
木造アパートの耐用年数は22年
耐用年数は資産の種類ごとに国税庁が細かく決められており、木造アパートの場合は22年に設定されています。つまり、木造アパートは建てられてから22年で帳簿上の価値が無くなるということです。
勘違いしやすいのですが、国税庁の耐用年数はあくまで税務上の目的で期間を設定した「法定耐用年数」であり、建物自体の寿命を指すものではありません。
木造アパートの物理的な耐用年数は一般的に50年程度といわれており、適切な修繕やメンテナンスを行うことで、22年を過ぎても使用することができます。ただし、法定耐用年数が過ぎると減価償却資産を計上できなくなるため、税負担が増加する可能性があります。
木造アパートの経営では、法定耐用年数と物理的な耐用年数のそれぞれの視点で経営戦略を立てることが大切です。
参考:東京都主税局 | 償却資産の評価に用いる耐用年数
参考:国税庁 | 主な減価償却資産の耐用年数表
耐用年数と減価償却資産の関係
減価償却資産は時間の経過とともに価値が下がる資産のことで、最終的に帳簿上では価値が0円となります。耐用年数は、減価償却資産の価値が帳簿上で0円になるまでの期間のことです。
木造アパートを賃貸事業のために購入すると、減価償却資産に分類されるため、耐用年数に応じて帳簿上の価値が徐々に減少していきます。
減価償却資産を耐用年数で分割した費用を「減価償却費」といい、毎年経費として計上することになります。
具体例を挙げて説明すると、減価償却資産である2,000万円の木造アパートの場合、耐用年数22年に基づき、毎年91万円(2,000万円 ÷ 22年)を減価償却費として計上するということです。
耐用年数を過ぎた木造アパートの価値は?
前述した通り、耐用年数(木造アパートでは22年)を過ぎた場合、帳簿上の価値は0️円となってしまいます。
そのため、23年目からは減価償却ができなくなり、減価償却費を計上もできません。しかし、これはあくまで帳簿上の話であり、不動産としての価値と混同しないように注意が必要です。
帳簿上の価値が無くなっても、まだ賃貸物件として使えるのであれば価値がありますし、売却することもできます。
耐用年数を過ぎてもアパート経営は可能
木造アパートの寿命は50年程度のため、だいたいの場合耐用年数の22年を超えても賃貸経営は可能です。しかし、築年数が長くなるほど修繕やリフォームが必要となるケースが増えてきます。
そのため、修繕費やリフォーム費などの支出と家賃収入のバランスを考慮し、赤字になる場合は売却も視野に入れたほうがよいでしょう。
耐用年数を意識した収支計画を立てることが大切
耐用年数の期間中と耐用年数を超えたあとでは、収支の内訳や物件の価値が変わってきます。
たとえば、耐用年数の期間中は築年数が比較的浅いため、修繕費も抑えやすく、賃貸需要が安定していることが多いです。耐用年数が経過した後は、築年数が20年を超えるので物件の価値を維持するため、リフォームや家賃の見直しが必要になるかもしれません。
耐用年数の前後でどんな変化があるのか、メリットやデメリット、建物やエリアの状況などを総合的に考えることが大切です。
耐用年数が過ぎた木造アパートを経営するリスク
法定耐用年数を超えて帳簿上の価値がなくなっても、アパート経営を続けていきたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、耐用年数が過ぎている物件で賃貸経営をする場合、いくつかのリスクも伴います。
ここでは、耐用年数が過ぎた木造アパートを経営するリスクについて解説していきます。
経費の項目が減るため税金の負担が増える
耐用年数の期間中は、減価償却費を毎年計上します。
減価償却費は経費として計上できるため、減価償却をすることで課税される所得を減少させることが可能です。
所得税額は、(収入−経費)×税率で計算されるため、減価償却費を計上している間は納税する所得税が少なくなります。
逆に、耐用年数が過ぎて減価償却ができなくなると、差し引ける分の経費が少なくなるため、税負担が増えてしまいます。
アパートの空室率が高くなる
耐用年数を過ぎたアパートを賃貸利用しても問題はありませんが、設備が古くなってしまっている場合は交換が必要です。
また、外壁が剝がれていたり壁にひびが入っていたりするときは、外壁リフォームをしなくてはいけません。見た目が悪いアパートは入居率が下がることで、家賃収入が減ることも考えられます。
アパートローンの延長は難しい
アパート経営を行う場合、住宅ローンではなくアパートローンを組んで購入するのが一般的です。
アパートローンでは、購入する土地と物件を担保にしてお金を借ります。物件が耐用年数を過ぎていると不動産としての評価は低くなります。
そのため、木造アパートの耐用年数が経過後、返済期間の延長ができないケースがあるのです。
修繕費などの出費が増えていく
アパートの経営期間の期間が長いほど、老朽化による問題が多くなってきます。築年数が浅いうちは問題が起きないかもしれませんが、故障した設備の修理や交換など軽微な出費は発生するでしょう。
一方、築古のアパートとなると一室を丸ごとリフォームしたり、水回りの設備を交換したりと、費用が高額になりがちです。
修繕費などの費用が膨れ上がることは、経営する上で大きなリスクといえるでしょう。
利回りは悪くなる傾向にある
以下の理由から、耐用年数を過ぎた木造アパートは利回りが悪くなることが考えられます。
- 建物の老朽化や設備の劣化により空室率が高くなる
- 大規模な修繕やリフォームが必要になり経費がかかる
- 築年数が古いことで建物自体の価値が低下する
上で挙げた理由から、利回りは経年とともに悪化する可能性があります。
このほかにも、周辺の競合物件より賃貸物件としての魅力が低いときは家賃を下げざるを得ないため、家賃収入が減少することで利回りも悪化するかもしれません。
木造アパートの耐用年数を超えたらどうすればいい?
耐用年数を過ぎても経営を続けた場合のリスクについて解説しましたが、木造アパートの耐用年数を超えた場合はどうすれば良いのでしょうか?
ここでは、耐用年数が過ぎた木造アパートの対処法について詳しく解説していきます。
木造アパートを建て替える
まず、木造アパートを新しく建て替えるという方法があります。建て替えることで新築のアパートとなるため、空室率を抑えることができるでしょう。
また、建て替えることで再びローンを組んでお金を借り入れることができますし、減価償却費を再び計上できるところも魅力です。
木造アパートを売却する
耐用年数を過ぎた木造アパートを売却するのもよいでしょう。
アパートの築年数が古くなってくると一般的に空室率が高くなり、修繕にかかるお金も増え、段々と利回りが悪くなってきます。
いっそのことアパートを売却し、売却金を元手にして新しく不動産投資を始めるのも有効な方法です。
木造アパートを解体して更地にする
木造アパートを解体して更地にすることで利用の幅が広がります。
たとえば、一戸建てを建てて自宅にするのもよいですし、貸しオフィスや駐車場にして新たな投資を始めるなど、さまざまな使い方できます。
また、更地のまま土地だけ貸し出すことも可能です。アパートの解体には費用がかかりますが、その分可能性が広がる選択肢といえるでしょう。
修繕などをして経営を続ける
建て替えや建物の解体、売却だけが選択肢ではありません。法定耐用年数は22年ですが木造アパートの寿命自体はもっと長い訳ですから、そのまま経営することもできます。
その際、賃貸経営を続けるリスクをきちんと把握し、対策していくことが重要です。具体的には、リフォームやリノベーションをしたり、入居者のターゲットを絞って空室対策をしたりします。
また、設備の点検を定期的に行い、壊れてから対応するのではなく、事前に対応できるようにするのが理想です。
木造アパートの対処法を不動産会社に相談してみる
アパートの売買に詳しい不動産会社に相談してみるのも1つの手です。
相談することで、木造アパートがあるエリアや立地を考慮して売却や買取など、適した方法を提案してもらえるでしょう。
木造アパートを取り扱った実績がある不動産会社に意見を仰いでみることで、思いもよらなかった選択肢に出会うこともあります。
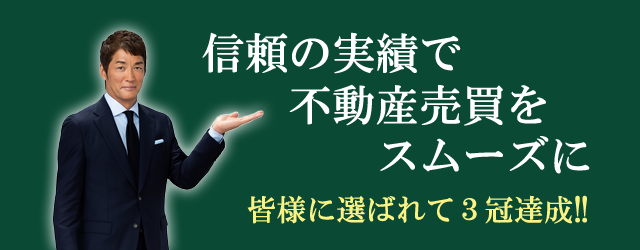

- 高値売却かつ早期売却したい方におすすめの不動産会社 No.1 ※
- 知人に紹介したい不動産売却会社 No.1 ※
- 相続の相談をお願いしたい不動産売却会社 No.1 ※
トップファーストでは、全国の一棟アパートや一棟マンションといった収益物件をはじめ、様々な不動産を取り扱っております。
相続や資産整理といった不動産に関するご相談も、実績豊富な当社にお気軽にお問い合わせください。高い専門知識を持ったスタッフが問題解決をお手伝いいたします。
2023年2023年5月期_ブランドのイメージ調査(調査1~3)
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査期間:2023年3月14日~2023年5月31日
n数:129(※調査1)、124(※調査2)、136(※調査3)/調査方法:Webアンケート
調査対象者:https://jmro.co.jp/r01446/
備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。